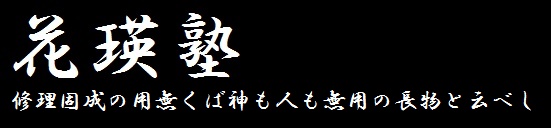11月も末となり、間も無く12月を迎える。慌ただしい12月となれば、年の瀬まであっという間である。時の経つは早いものだ。
徳川家康が征夷大将軍に宣下された1603年から3年間、琉球王国に渡った浄土宗名越派の僧侶・袋中は、1608年前後に琉球への仏法の渡来や琉球の神祇などを論じる『琉球神道記』とともに、消息型往来物といわれる手紙形式の琉球情報書『琉球往来』を著述した。
袋中『往来』は『神道記』に比べ陽の目を見ることはなかったが、江戸時代後期、いまから207年前の文化6年(1810)12月、国学者・伴信友が京都にて『往来』を入手したことが記録されている。信友はその他にも新井白石による琉球研究書『南島志』を受容した上で、日本と琉球あるいは朝鮮や中国などの関係を論じる『中外経緯伝』を天保9年(1838)に著すなど、琉球への強い関心を有していた。
先学の指摘によると、信友は『経緯伝』にて、白石『南島志』を琉球が「皇国風に化り」「臣国となりぬる」由来、つまり琉球が日本へ従属し感化される由来を説く書であると曲解する。そして琉球の「皇国風」の初発として琉球王国最古の正史『中山世鑑』などを史料として駆使しながら、源為朝が琉球に渡り、その子が琉球で舜天王として王朝を開いたとする「為朝渡琉譚」を論じ、さらに為朝に由来する舜天王統から第二尚氏までの血統的一系をいい、現在に至る琉球の「皇国風」を理由づける。
『世鑑』は第二尚氏・尚質王の時代に、当時の摂政・向象賢(羽地朝秀)が編纂した正史であり、その内容は確かに冒頭に為朝渡琉譚を引き、その子・舜天王から第二尚氏に至るまでの万世一系的な王統論を展開している。しかし先学の指摘によれば、さしもの向象賢も『世鑑』において舜天王統・英祖王統・察度王統・第一尚氏・第二尚氏という琉球の王統交替を無視しえず、英祖王の日光感精型神婚譚や察度王の天人女房譚など天子感生説をもって各王統の始祖物語を記述し、始祖を聖化・特別視している。『世鑑』はけして安易な日琉同祖論を論じるものでも、舜天王統から第二尚氏までの万世一系を論じる史書でもなく、「矛盾を孕む」史書である。
さらに近年、従来の琉球言説を琉球―日本や琉球―薩摩といった一対一対応ではなく、東アジアの視点から読み直す試みがなされている。確かに上述の袋中『往来』など近世の琉球言説や琉球情報からは、琉球―日本―朝鮮‐中国はてはフィリピン・ルソンが登場する。薩摩の琉球侵略を語る「薩琉軍記」など「侵略文学」においても、秀吉の朝鮮侵略と薩摩の琉球侵略を絡めつつ、薩摩―朝鮮―琉球の関係が語られるなど、琉球と東アジアの複合関係が容易に読み解ける。
正史『世鑑』がいう英祖王など琉球各王統始祖の日光感精型神婚譚なども東アジア各地で見られる天子感生説である。例えば北魏の太祖道武帝、漢の武帝、高句麗の始祖・朱蒙など、日光感精型神婚譚はモンゴル、中国、朝鮮などに見ることができる。日本においても天之日矛伝承が日光感精型神婚譚を語り、他にも中世において散見される。かかる事実や指摘を踏まえることにより、信友が袋中『往来』を手にした文化6年12月より207年後の12月を控え、東アジアと対抗・対決するアメリカ軍が配備された沖縄―日本ではなく、また従属・感化をもって語られる沖縄―日本ではなく、東アジアそのものとしての複合関係的な東アジア―沖縄―日本を考えていきたい。