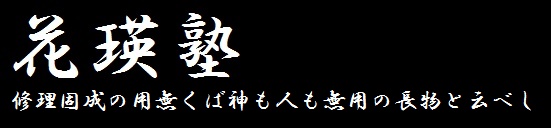来たる10月17日、令和元年(2019)11月に亡くなった中曽根康弘元首相の内閣・自由民主党合同葬がおこなわれる予定となっている。

中曽根元首相の合同葬は、もともとは本年3月におこなわれる予定であったが、コロナの感染拡大にともない延期となっていた。
ところが、延期されていた合同葬が10月17日にあらためておこなわれることや、合同葬の予算の半額である約1億円が政府予備費から支出されることが明るみになった本年9月以降、合同葬に対する社会的な批判の声が高まった。
元首相の内閣・政党合同葬など一定の公職者の公的な葬儀そのものを一切おこなってはならないというつもりはない。これまでも元首相の内閣・政党合同葬や国会議長の議院葬など各種の公的な葬儀はおこなわれており、例えば平成30年の翁長雄志前沖縄県知事の県民葬など非常に感動的で後世まで語り継いでいきたい公的な葬儀があったことも事実だ。
コロナ禍のなかで
しかし、公的な葬儀は、そうであるからこそ、広く国民の理解や納得に基づくものでなければならない。このたびの中曽根元首相の合同葬も、そもそもコロナの感染拡大にともない延期された経緯からしても、コロナ禍という現在の社会情勢とそこにおける国民感情をよく考慮しておこなわれるべきだ。
今なお連日数百人単位でコロナ感染者が出ており、亡くなる方も少なくない。多くの人々がコロナ禍で外出制限を強制され、それにともない商店・企業が売り上げを落とし、倒産・廃業などの件数も上昇した。コロナ関連の解雇・雇止めも現在では6万人を超える状況となっている。
そればかりではない。コロナの感染を防ぐため、入院患者へのお見舞いを制限する病院もあり、重篤な病により入院中の肉親を満足にお見舞いすることができないまま永遠の別れを迎えた家族もある。また、そうして亡くなった肉親の葬儀もコロナのために十分におこなうことができず、ごくごく近親者のみで簡単に済まさざるを得なかった事例もある。
そうしたなかでのこのたびの中曽根元首相の合同葬。あまりに時宜ふさわしからず、社会的な批判や疑問視、あるいは不満の声が高まるのは当然といえよう。
合同葬の予算への批判について
合同葬への約1億円の政府予備費の支出についても、予備費は全額コロナ対策へ宛てることを野党が求めていた経緯や、これまでの政府のコロナに関する経済対策の不十分さもあり、予備費10兆円のうちの1億円とはいえ、「その1億円があれば他に助かった命もあったというのに」という社会的な怒りが沸き起こるのも理解できる。
一部では「合同葬に関する約1億円の予備費支出は当然だ」、「そんなことで不満が出るのは日本が貧しくなった証だ」などとあたかも合同葬や合同葬への予備費支出への批判を「庶民のひがみ」とでもいわんばかりの冷笑・嘲笑も散見されるが、合同葬や合同葬に関する予備費支出の問題はそのような低俗なものではなく、つまるところ現前のコロナ禍という社会情勢のなかでのあまりに無能かつ酷薄な政府のあり方への批判や不満、不信、あるいは新自由主義・自己責任社会を目指す菅首相の政治姿勢への批判などに基づくものであり、人々の「根底的な怒り」を見ていかなければ批判の意味も理解できないだろう。
弔意表明の求めと人々の警戒
また、このたびの合同葬に関し、政府は関係機関に弔旗の掲揚や黙とうの実施など、弔意表明を求めている。これにともない文科省が全国の国立大学などに弔意表明を求めたことも明らかとなった。

こうした政府による弔意表明の求めは、過去の首相の合同葬でもおこなわれており、中曽根元首相の合同葬においてだけ特別に政府が弔意表明を求めているわけではないことには留意したい。
政府による合同葬での弔意表明の求めにあたり、明治天皇の崩御にともなって弔旗掲揚の方法としてさだめられた大正期の閣令「大喪中ノ國旗掲揚方ノ件」(大正元年7月30日閣令第1号)も周知されているが、これも例えば小渕恵三元首相の合同葬や東日本大震災の追悼式などで政府が関係機関に弔意表明のやり方として周知しているものでもあり、殊更に何かということはない。
ただし、それではなぜこのたびの合同葬での政府による弔意表明の求めに対し、社会的な批判の声が高まっているのかということも考える必要があるだろう。
それは、そもそも政府による弔意表明の求めが人々の内心の自由を侵害するおそれがあることや、これまで述べてきたようなコロナ禍との関連における政府への批判・不信に基づいていることはいうまでもないが、そればかりではなく、最近の日本学術会議の会員任命について特定の人物の任命を政府が拒むなど、菅首相によるファッショ的統制が進むなかで、政府による弔意表明の求め、すなわち政府による内心の自由の侵害、介入に対する警戒が強まっているからともいえる。
国民の理解に基づく公的葬儀を
いずれにせよ、現在のコロナ禍という社会情勢とこれに対する無能かつ酷薄な政府の対応という政治のありように対する社会的批判・不満・不信が根強くあり、さらに菅首相の新自由主義・自己責任社会への志向、そしてファッショ的統制が進行するなかでは、このたびの合同葬に対する国民的な理解や納得は得られない。そして国民的な理解や納得に基づかない公的な葬儀はありえない。
過ちをあらためることをためらう必要はない。今からでもこのたびの合同葬の時宜、あり方を再考すべきだ。「もう決めたことだから」、「今までやってきたことだから」という言い訳は通用しない。そうした“悪しき前例主義の見直し”は、菅内閣のスローガンであったはずだ。